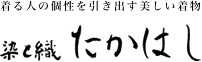トップページ > 商品紹介 > 浅岡明美 綾織九寸名古屋帯(縞)
浅岡明美 綾織九寸名古屋帯(縞)
商品説明
瑞々しい白地を背景に縞模様が織り出されています。辺りを山に囲まれた静かな環境で、糸作りから織りまでを一人でこなす浅岡明美さんの九寸名古屋帯地です。
1960年、千葉県で生まれた浅岡さん。女子美術大学でデザインを学び、卒業後、民藝の父と呼ばれた柳宗悦の甥、柳悦博氏に師事されます。
『柳先生は見て覚えなさいという感じの人で、私は分からないことがあるとすぐ柳崇さんに尋ねていました。崇さんはとても丁寧に教えて下さるんです。笑 先生が二人という贅沢な感じでした。崇さんには今でも何かあると直ぐに電話をしています。もしかしたら煙たがられているかもしれません。笑』
決して飾らず自然体。そんな彼女の雰囲気が作品にも表れています。独立後は自宅兼工房で制作を続けられています。

光によって表情を変える色…
綾織と呼ばれる織組織を得意とする浅岡さん。艶のある地風と、光によって生まれる陰影が作品の色に深みを与えています。
『糸作りはとても時間がかかります。そして仕上がりを左右する大切な仕事。「良い糸を丁寧に準備してあげると、美しい作品になるよ。」そんな先生の言葉はよく覚えています。』
染料は植物染料を基本に、化学染料も重ねるなど、独自の色彩と堅牢度を高める実用性を兼ねた美しさを追及されています。

結城縮と合わせて…
こちらの帯地は私のオーダーで浅岡さんに誂えて頂いた作品です。
「浅岡さんの出す赤の色が好きなので、そのイメージで縞をお願いできませんか…」そんな私のオーダーに、浅岡さんが見事に応えて下さいました。
まず目に映るのは、白と赤紫の美しい色のバランス。そしてよく見ると単純な縞ではなく、細かな経絣が所々に織り込まれ、帯地に深みを与えています。
きっと私の拙い写真では、この帯地の美しさの半分もお伝えできていないと思います。織物から小紋や色無地などに合わせて…お手持ちのお着物とのコーディネイトなど、お気軽にご相談下さい。
浅岡明美(あさおかあけみ) 略歴
1960年 千葉県に生まれる
1982年 女子美術大学卒業後、織物を志し柳悦博氏に師事。独立後国展に4度出品・入選。
2008年 グループ展「風と桜の會」
2010年 グループ展「風と桜の會 第2回」
現在 千葉県内にて創作活動
■お仕立てについて
弊店にて検品後、弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。帯芯の堅さや、寸法のご相談などございましたら、お申し付けください。
■お手入れについて
日常のお手入れは、部分的なしみ落としで十分です。長期間の保存の前や、全体の汚れが気になる場合は、ドライクリーニングをお薦めしています。ご家庭での水洗いは出来ませんので、ご注意下さい。
■色について
HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。*パソコンで綺麗に表示されない場合、iphoneやスマートフォンからアクセスして頂くと、綺麗に表示される場合があります。
■お手元での商品確認サービス
こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。
■在庫について
実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。
浅岡明美 綾織九寸名古屋帯(縞)
- 【素材】
- 絹100%
- 【生地巾】
- 約34.5cm
- 【生地丈】
- 約3.7m
- 【価格】
- 売切御礼
この商品をみたお客様は、こんな商品もみています
-
紗綾型に菊と蘭(本紋地紋)を織り出した綸子地に、“七宝文”が絞り染めと刺繍によって描かれています。京都らしい艶やかな配色と絞りの柔らかな輪郭線が美しい、九寸名古屋帯です。友禅染めが生まれる・・・
-
しっとりと深みのある藍鉄色の地に、綾織と呼ばれる織組織で細かな"組違い小市松文様"が織り出されています。美しい艶と透明感のある色彩。菊池洋守さんの八丈織です。菊池洋守さんは、1940年東京都八・・・
-
京友禅らしい淡い砥粉色の地に、心地よい間隔で唐花模様が描かれています。京友禅の老舗、工芸キモノ野口の小紋着尺です。工芸キモノ野口は、享保18年(1733年)初代金谷安部兵衛が京・油小路四条上ルにて呉服商を・・・
-
きもの好きにとって小物の収納は頭の痛い悩みです。出来るだけコンパクトに、かつ分かりやすく…そんなお客様の声から生まれた弊店オリジナルの万能桐小物箱。取り外しが可能な仕切り付の収納箱二段に深め・・・
-
さらりとした綿麻生地に、「波杢目立巻絞り」と呼ばれる伝統的な技法で、不規則な縞柄が染められています。夏らしい白と藍、シンプルですっきりとした絞り染めの浴衣地です。友禅染めが生まれるよりもはるか昔か・・・
-
「今どきこんな美しい布はめったにないのです」民藝運動の父、柳宗悦の著書「芭蕉布物語」の一節です。沖縄県大宜味村喜如嘉(きじょか)。ここで平良敏子さんを中心に、かつて柳宗悦が訪れたこの地でみた芭蕉布の・・・